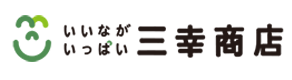「人の心に貯金する」 サンコーの歩み
サンコーは1962年の創業以来、生活サポート用品の開発・製造・販売を通して皆さまの生活に寄り添い、地域社会への貢献を積み重ねてまいりました。こちらではそんな弊社の、半世紀以上に渡る『歩み』をご紹介させていただきます。
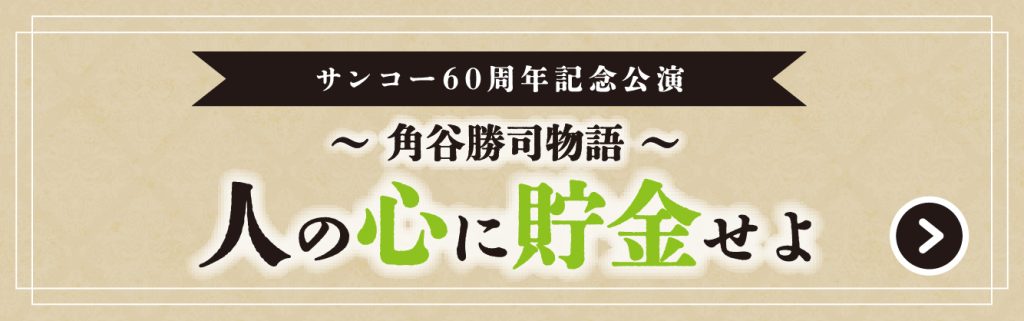
沿革
| 1962年 3月 | 角谷勝司が和歌山県海南市阪井で創業 「キッチンダスター」発売 |
| 1963年 | 「扇風機カバー」発売 |
| 1965年 | 「洋式便座カバー」発売 |
| 1966年 | 「電話機カバー」発売 |
| 1967年 4月 | 資本金500万円でサンコーを設立 |
| 1970年 5月 | 資本金を1,000万円に増資 |
| 1971年 3月 | 資本金を1,500万円に増資 |
| 1972年 4月 | 東京営業所開設 |
| 1972年 6月 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 1973年 7月 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 1974年 7月 | 資本金を4,500万円に増資 |
| 1976年 6月 | 東京都江戸川区に自社ビルを建設 東京営業所移転 |
| 1979年 4月 | サンコーテリア株式会社設立 |
| 1983年 4月 | サンコー新本社完成 |
| 1987年 4月 | サンコーをサンリビア株式会社に社名変更 C.I.導入 関連会社を含め8社で三幸グループを結成 |
| 1992年 | 「おくだけベンザシート」発売海南市とサンコーの歴史 |
| 1993年 | 「びっくりフレッシュ」シリーズ発売 |
| 1998年 4月 | 現在地(海南市大野中)にグループ本社新築移転 |
| 2002年 4月 | サンリビア株式会社を核に3社を統合しサンコーに社名変更 資本金を6,500万円に増資 |
| 2003年 4月 | 関連会社2社をサンコーに統合 資本金を9,500万円に増資 |
| 2006年 6月 | 東京I.O.C.開設 |
| 2008年 7月 | サンコーピーエム株式会社設立 |
| 2009年 4月 | 角谷太基が代表取締役に就任 角谷勝司が相談役に就任 |
| 2014年 1月 | 海南市阪井に社員寮建設 |
| 2014年12月 | サンコーピーエム 岸和田工場新設 |
| 2016年 4月 | 関連会社1社をサンコーピーエム株式会社に統合 |
| 2018年12月 | 関連会社1社をサンコーに統合 |
| 2020年1月 | 海南市阪井に新倉庫完成 |
| 2021年4月 | 海南市且来に新事務所・倉庫完成 |